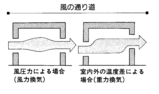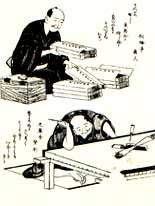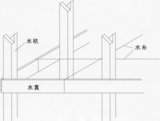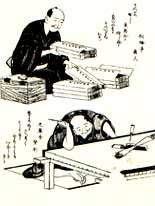
省エネ住宅・エコ住宅とは①
省エネルギー、エコロジーと言う言葉が多く使われていたり、聞いたりします。
特に、地球温暖化問題で、なるべくエネルギーを使わないとか、地球環境に対してなるべく負荷の少ないエネルギーを使いましょうと言う考え方が多くなってきています。
そこで、省エネルギー、エコロジー(この言葉は色々な意味を持っているのでここでは地球にやさしいという意味で使いたいと思います)住宅というのはどうゆうものがあるのか、何回かに分けてお話ししてゆきたいと思います。
まず始めに、省エネルギー・リサイクルという言葉から、今から少し前、150~400年ほど前、日本は江戸時代でした。
この江戸時代非常にエコロジーな生活をしていたらしいのです。
ただ、現代の人が江戸時代と同じ生活をしろと言われてもできないと思います。
でも、その時代の生活を知ることにより現在の住宅や生活に取り入れても良いのではないかと、思える物も有ります。
1回目として食物連鎖という話をします。
まず、食料ですが現在の日本の食糧自給率は4割程度、残り6割を輸入でまかなっています。
江戸時代当然全て自給していました。
そして、その自給方法も日本人の主食である米と野菜などを人が食べ、排泄物となり下肥として、近隣の農家の人たちが回収に来て、肥だめで発酵させ、田んぼや畑の肥料として使っていました。
その肥料がまた、植物を育て人間や家畜の食料として還元してゆく、小学校の時、食物連鎖という言葉を教わったと思います。
それ以外にも、稲のわらは、肥料としても使いましたし、わらじ、わらぐつ、蓑、などの衣料品、俵などの梱包品納豆を入れる入れ物、畳の芯に使われたり、縄として物を縛ったりと様々な物に利用され、それも使い終わったらたき付けなど燃料としても使われ、燃料として使い終わった灰も回収され肥料として使われたり、まさに何も捨てる物が無くその年でできた物はその年に消費するリサイクル社会が確立されていました。
さて、現在はどうでしょう、今問題になっている、中国製野菜、遺伝子組み換え食品、生産者がどこの誰だか解らない輸入食品、石油からできた肥料を使い、化学殺虫剤を使い、生産された食品は本当に安全なのでしょうか。
江戸時代、いや、40年ぐらい前まで私の住んでた所にも肥だめがあり、その肥料で稲を作っていました。
蛔虫の元となるので下肥は止めて化学肥料が安全というのは本当?
殺虫剤とは虫だけ殺すのですか?
人間が摂取すれば殺人薬になるのではないですか?
江戸時代の生活に100%戻れと言っても、戻れません。
でも、安全・安心な食生活をするにはどうすればよいか。
化学肥料を止め、殺虫剤も使わないようにする。
虫食いがあったりして当然見栄えの悪い野菜ができるでしょう。
毒の付いている生産者の解らない見栄えの良い野菜と、自分たちや生産者の顔が解る、農薬の付いていない見栄えの悪い野菜とどちらの方が、安全で安心できる食品なのでしょうか。
値段の問題、販売するところの問題色々問題がありすぐに、江戸時代のようなリサイクル社会を作るわけにはいきません。
でも、一人一人が考えできる範囲で行動してゆくことが大切だと思います。
次回、建物の省エネルギーについて話していきたいと思います。
読売理工医療福祉専門学校:建築系学科