遅くなりましたが、最後に法規についてです。
■初めて見る形式の問題もあり、昨年度と同様にやや難しいようである。ここ数年は、毎年のように新しい傾向の問題が出題され、全体的に難易度が上がったように感じられる。だが、過去に出題されたパターンの問題も多く、落ち着いて解答すれば十分高得点に達することはできる。
●建築基準法に関する出題は23問で、一般構造に関する部分(問題5~8)に新傾向の問題が多い。また、最近は斜線制限の問題(問題22)が複雑になっている。過去問と同じ形式の問題の中に、受験生が引っかかりそうな選択肢が見られるので注意が必要である。
問題1は用語の定義に関する出題で、基本的な問題。答は2。「準耐火性能」の説明が耐火性能の説明になっている。
問題2も基本的な問題で、答は4。鉄骨造で階数が2であるから、この建築物は法6条1項三号に該当し、大規模の模様替をするには確認申請が必要となる。
問題3も基本的な問題。答は5である。小規模なペントハウスは階数に算入されないが、この場合のペントハウスの水平投影面積は30㎡で、建築面積の1/8以上となるため階数に算入する必要がある。従って階数は4となり、誤り。
問題4は難しくはないが、慌てていると間違える。
イ.は規則1条の3表の1に書かれている。正しい。過去にも出題されたことがあるが、施行規則を見たことがないと探すのに苦労する。 ロ.工事届のことであるから、法15条により、施工者ではなく建築主が届け出なければならない。誤り。 ハ.仮使用承認は、一般的に、特定行政庁に提出するものだが、完了検査の申請をした後は建築主事に提出する。誤り。法7条の6第1項一号のカッコの中に書かれているので見落とさないように注意しよう。 ニ.工事完了4日以内に指定確認検査機関へ完了検査の申請をすれば、建築主事に申請する必要はない(法7条の2第1項)。正しい。
従って、イとニが正しいので、答は3となる。
問題5の答は2。過去には出題されていない配管設備の問題であるが、学科Ⅰ計画で給排水設備の勉強をしていれば、法令集がなくても分かる(令129条の2の5第2項一号)。
問題6の採光計算は、隣地境界線から建築物までの距離を計算する問題で、採光計算の方法が改正されてからは初めての出題となる。改正前では、このパターンの問題が平成9年度に出題されている。過去の出題パターンを研究していた人にとっては想定の範囲内であるが、準備をしていなかった人にとっては難しい問題。
距離Xを含む方程式をたてて、解けばよい。この保育室に必要な有効採光面積は、保育室の床面積の1/5であるから(令19条3項の表の(2))、70×1/5=14。近隣商業地域における採光補正係数は、 水平距離/垂直距離×10-1.0 であり、採光補正係数に窓の面積(5㎡)をかけたものが有効採光面積になる。従って、有効採光面積は {(X-0.5)/5×10-1.0}×5 となり、この値が必要な有効採光面積(14㎡)と等しいときに、Xは最小となる。よってX=2.4となり、答は4となる。
問題7は換気設備の問題だが、住戸の平面図を見て考える、新しい傾向の問題。今までにない出題形式であるため、どのように解けばよいのか分からない受験生が多かったのではないだろうか。だが、シックハウス対策のため、居室には原則として換気設備が必要であることを知っていれば、3と4は消去できる。また、居室ではない 1.台所、2.便所、5.浴室 について、便所には換気設備が必要であることを知っている人も多いから、1と5に絞れる。5の文章をよく読めば、燃焼器具が室外に設置されているため、換気設備は不要であると判断できる。ある程度勉強した人であれば法令集を見なくても、5が答だとすぐに分かる。
問題8は難問である。まともに法令集を調べていたのでは、時間が足りない。直感に頼るしかないだろう。選択肢1に書かれている通り、石綿、クロルピリホス、ホルムアルデヒドは、有害な化学物質として建築基準法で規制されている(令20条の4、令20条の5)。新たに建築する部分には、これらの物質に対して規制がある。選択肢2は石綿を添加した材料に対する規制(法28条の2第二号)、選択肢3は多量のホルムアルデヒドを発散させる材料(第一種ホルムアルデヒド)に対する規制(令20条の7第1項一号)である。なお、問題文に空調が中央管理方式ではないとあるので、令20条の7第5項は適用されない。既存の建築物に対しては、一般に、既存不適格の規定(法3条2項)により、法の適用除外となる。さらに、既存不適格建築物に対する増築などの場合には、緩和措置がある(法86条の7)。だが、既存部分に対する石綿使用の緩和措置は(令137条の4の2)、増築部分の面積の制限や既存部分への措置などの条件があり(令137条の4の3)、選択肢4のように、既存部分への対策が必要となる。既存部分のクロルピリホスとホルムアルデヒドの使用については、令137条の15のカッコ書きにより令20条の7から令20条の9(ホルムアルデヒドに対する技術的基準)に限定されているため、クロルピリホスには技術的基準が適用される。従って、選択肢5の記述は誤りである。答は5。
問題9は木造に関する問題だが、平成10年度に出題されている問題とほぼ同じである。答は1。
問題10は鉄筋コンクリート造の基本的な問題であるが、4と5に「軽量骨材を使用する場合」と書かれていることに注意。これを見逃すと混乱してしまう。4は令73条3項を調べ、同条4項を見落とさないように、5は令74条1項一号を調べ、カッコ書きを見落とさないようにする。答は4である。
問題11は避難規定の基本的な問題で、答は2である。令126条の4第三号より、「学校等」には非常用照明が不要であり、令126条の2第1項二号により、ボーリング場は学校等に含まれる。従って、ボーリング場には非常用照明を設けなくてもよい。
問題12は、法24条の制限に関する基本的な問題である。イ.が同条二号に、ロ.が同条一号に該当するため、防火構造にしなければならない。従って、答は1。
問題13は内装制限の基本的問題。3が答である。児童福祉施設は、令115条の3第一号により、別表第1において、(2)の病院などと同じ分類になる。よって、令128条の4第1~3項により、規模に応じて内装制限を受ける。
問題14は道路等に関する問題で、答は5である。これは過去に出題されたことがある(法68条の7第4項)。2では、建築審査会の同意について記述がなく迷うが、特定行政庁は建築審査会の同意を得なければ許可できないと考えれば、「特定行政庁の許可を受ければ」という記述だけでも間違いではない。
問題15と16は用途地域に関する問題である。問題15は4、問題16は5が答となる。
問題15の4では、別表第2(り)項二号で150㎡をこえる工場が禁止されているが、300㎡以下の自動車修理工場は建築できるとカッコ書きにあるので注意。また、問題文の300㎡を読み落とすと、2も新築することができると勘違いしてしまうので注意。第二種低層住居専用地域では、学習塾や店舗などに対して150㎡以内の制限がある。問題16は、敷地が2つの地域にわたる場合だが、初めて設問の図中に建築物が描かれ、受験生を混乱させる問題になった。用途地域の制限では建築物の位置には関係なく、広い方の地域の制限に従うことを知っていれば、第一種中高層住居専用地域に旅館などを建築することができるか、という問題になる。
問題17と問題18は、面積制限の計算問題で、どちらも基本的な問題である。答は、問題17が3、問題18が2となる。ここでは、2項道路に面する場合の敷地面積を間違えないように注意。
問題19~21は、比較的簡単な問題が続いている。
問題19は、高さ制限や日影規制に関する問題で、答は4。別表第4から、4mではなく、1.5mと分かる。問題20は、建ぺい率や容積率などに関する問題で、答は1。問題21は、防火・準防火地域内の制限の問題で、看板等は不燃材料にしなければならない(法66条)ので、答は3。
問題22は高さ制限の計算問題で、道路斜線制限の検討を行なう。ただし、設定が複雑で、出題に疑問もあり、難しい問題である。道路からの高さが1.4mの生垣が道路に沿ってあり、後退距離の算定にあたり、これが令130条の12第三号でいう「網状その他これに類する形状であるもの」に該当するのかどうか迷う。一般的に該当すると考えられるが、条文には明記されていないので、試験の問題として出題するのは如何なものか? 後退距離は、建築物と道路の最短距離をとるので2mとなり、また、道路の反対側に川があるため、敷地と反対側の道路境界線は、川の向こう側の境界線となる(令134条)。従って、基準となる点は、川の向こう側の境界線から敷地と反対側に2mの地点となる。この基準点とA点との距離は、2+2+4+2+2=12(m)であるから、道路斜線制限による高さの限度は、12×1.25=15となる。しかし、敷地と道路との間に0.4mの高低差があるため、地盤面からの建築物の高さは、15-0.4=14.6(m)となる。高低差が1m以上ないので、高低差による緩和措置は適用されない。答は3。
建築基準法最後(問題23)は、建築基準法全般に関する問題で、災害時に焦点を当てた新しい視点からの出題である。 イ.被災市街地における建築制限(法84条)の内容で、初めての出題。正しい。 ロ.非常災害時の応急仮設建築物(法85条1項)に関して、防火地域内に建築する場合は建築基準法令が適用されてしまう。誤り。 ハ.災害時の停車場に関する扱いは、法85条2項にあり、適用されない条文の中に法6条が含まれているので、確認申請が必要ではないと分かる。正しい。 ニ.災害時の官公署に関する扱いは、ハと同様に法85条2項にあるが、同条3項により、工事完了後3月を超えて存続しようとする場合に、特定行政庁の許可が必要となる。誤り。従って、答は2となる。
●関係法令からの出題は、問題数が少ない上、2種類の法律しか出題されなかったので、条文を探す時間も短くて済み、また、基本的な内容的であった。
問題24は毎年出題される建築士法の設問で、答は5である。他人の求めに応じ報酬を得て設計などをする場合、事務所登録が必要となる(建築士法23条1項)が、建築士本人が建築主となる場合は登録の必要はない。
問題25は、いわゆる品確法の問題である。答は3。「工事の完了した時から」と書かれているが、「注文者に引き渡した時から」の誤りである(品確法94条1項)。
 ハガキのイス 作り方
ハガキのイス 作り方
 の模型ができるハガキを送らせていただきました。
の模型ができるハガキを送らせていただきました。 きれいに作れましたか
きれいに作れましたか これ以外にも、かわいいイスや、建物の模型を用意していますので、ぜひ本校の体験入学に参加して下さい。
これ以外にも、かわいいイスや、建物の模型を用意していますので、ぜひ本校の体験入学に参加して下さい。 
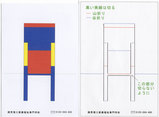
 7月28日、29日の二日間VEリーダー受験資格取得の講習会が開かれました。
7月28日、29日の二日間VEリーダー受験資格取得の講習会が開かれました。 VEとは、バリューエンジニアリングで、日本語で言えば「価値工学」のことです。VEの定義は、①最低のライフサイクルコストで、②必要な機能を確実に達成するために、③製品やサービスの、④機能的研究に注ぐ、⑤組織的努力であると定義されています。がこれでは、まだなんだか解りませんよね
VEとは、バリューエンジニアリングで、日本語で言えば「価値工学」のことです。VEの定義は、①最低のライフサイクルコストで、②必要な機能を確実に達成するために、③製品やサービスの、④機能的研究に注ぐ、⑤組織的努力であると定義されています。がこれでは、まだなんだか解りませんよね 、VEの概念式はV=F/Cという公式があります、これは、V:価値、F:機能、C:コストを式で表したもので、価値を上げるには4つのパターンがあります。①機能を変えずにコストを下げる、②機能を良くし、コストも下げる、③機能は良くするがコストは変えない、④機能を大幅に良くするが、コストが少し上がる、の4つになります
、VEの概念式はV=F/Cという公式があります、これは、V:価値、F:機能、C:コストを式で表したもので、価値を上げるには4つのパターンがあります。①機能を変えずにコストを下げる、②機能を良くし、コストも下げる、③機能は良くするがコストは変えない、④機能を大幅に良くするが、コストが少し上がる、の4つになります 。業務改善では、余計なこと、無駄なことが無いかを見つけ、改善を考える。コスト削減では、営業、設計段階での提案、請負業者の提案、が有ります。VEの実施手順としては、機能定義をして、機能評価をし、代替案作成して、提案をするという手順になります。実際には、グループを作りある課題に対して、価値を上げるにはどうしたらいいのかという色々な提案をして、案を作成してゆく作業になります。
。業務改善では、余計なこと、無駄なことが無いかを見つけ、改善を考える。コスト削減では、営業、設計段階での提案、請負業者の提案、が有ります。VEの実施手順としては、機能定義をして、機能評価をし、代替案作成して、提案をするという手順になります。実際には、グループを作りある課題に対して、価値を上げるにはどうしたらいいのかという色々な提案をして、案を作成してゆく作業になります。 。
。
 卒業生と飲み行きました
卒業生と飲み行きました に移動し二次会を行い近況の報告を行いました。そのメンバーの内、なんと今年、家
に移動し二次会を行い近況の報告を行いました。そのメンバーの内、なんと今年、家 を新築した卒業生が2人もおり、その、新居に今度みんなで
を新築した卒業生が2人もおり、その、新居に今度みんなで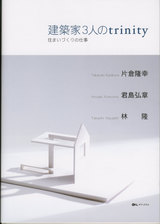
 本校卒業生 林隆さん の本が出版されました
本校卒業生 林隆さん の本が出版されました 六本木ヒルズ森美術館で行われている、「ル・コルビジェ展」見学会をSD研究会主宰で行いました。夜間の学生も参加して、普段昼間部の学生と夜間の学生が話すことはあまりないのですが、今回見学会の後、懇親会で仲良くなりました。
六本木ヒルズ森美術館で行われている、「ル・コルビジェ展」見学会をSD研究会主宰で行いました。夜間の学生も参加して、普段昼間部の学生と夜間の学生が話すことはあまりないのですが、今回見学会の後、懇親会で仲良くなりました。
