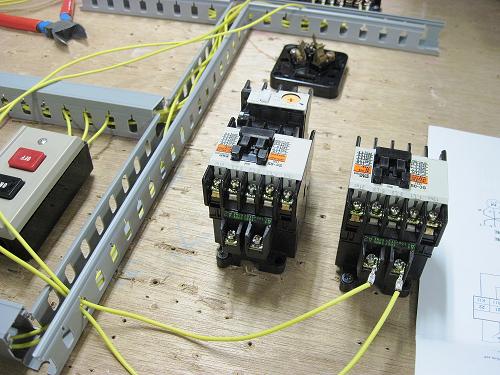建設業就業者数は平成9年の685万人から、22年には498万人まで減少し、その後ほぼ横ばいを続けて、27年には500万人であると、国土交通省は「適正な施工確保のための技術者制度検討会」第13回検討会資料5-2「現状の課題」で報告しています。
建設業就業者数は平成9年の685万人から、22年には498万人まで減少し、その後ほぼ横ばいを続けて、27年には500万人であると、国土交通省は「適正な施工確保のための技術者制度検討会」第13回検討会資料5-2「現状の課題」で報告しています。
この内、技術者数は平成9年には41万人、22年には31万人、27年には32万人であり、全体の就業者数と同じ傾向で推移していることが理解できます。
この資料では、建設業就業者数の55歳以上が約34%(全産業では約29%)、29歳以下が約11%(全産業では約16%)と高齢化が進行しているため、次世代への技術承継が大きな課題とされています。
総務省の「労働力調査」を元に国土交通省で算出した結果によれば、60歳から64歳までの建設業就業者数が35.7万人、65歳以上が42.4万人です。この約78万人の大半が10年後には引退すると見込んでいますが、29歳以下の就業者数はこの半数以下しかいません。
国土交通省ではこの検討結果を受けて、2級の施工管理技術検定の受験資格を緩和すると共に、試験回数も年1回から2回に増やしたりするなどの対策を既に講じています。
また、企業側としても、労働時間の減少と、休日を確保するための取組を、労働組合と一体となって開始しています。
かつては、元請が施工管理と施工の一部を行っていましたが、徐々にそれは下請に移行し、専門工事の施工管理も下請に移行してきているため、施工管理職の需要は益々高くなってきているといえます。

 電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。
電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。 電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。
電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。 ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。
ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。 普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。
普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。 本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。
本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。 電力会社や工場、ビルなどの電気工作物の保安監督を行える電気主任技術者(電験)有資格者は、第二種、第三種ともに、中長期的にも想定需要に対して十分に存在していると経済産業省は発表しています。
電力会社や工場、ビルなどの電気工作物の保安監督を行える電気主任技術者(電験)有資格者は、第二種、第三種ともに、中長期的にも想定需要に対して十分に存在していると経済産業省は発表しています。 電気主任技術者とは事業用電気工作物の保安監督のために配置することが電気事業法で定められています。
電気主任技術者とは事業用電気工作物の保安監督のために配置することが電気事業法で定められています。