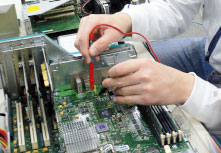 電気工事に似ているものに電気通信工事があります。
電気工事に似ているものに電気通信工事があります。
国土交通省の「建設工事の例示(建設業許可事務ガイドライン)」によれば、電気工事と電気通信工事の例としては次のとおりです。
電気工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
電気通信工事
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
ビルやマンション、住居内の電気工事は、構内電気設備と呼ばれています。
電話やインターネット、テレビ関係は電気通信工事に含まれます。
電気工事と電気通信工事は法的にも分離されており、電気通信関係の資格がなければできない電気通信の仕事があります。
平成31年度からは電気通信工事施工管理技術検定も開始され、電気通信工事施工管理技士が誕生します。

 建設業就業者数は平成9年の685万人から、22年には498万人まで減少し、その後ほぼ横ばいを続けて、27年には500万人であると、国土交通省は「適正な施工確保のための技術者制度検討会」第13回検討会資料5-2「現状の課題」で報告しています。
建設業就業者数は平成9年の685万人から、22年には498万人まで減少し、その後ほぼ横ばいを続けて、27年には500万人であると、国土交通省は「適正な施工確保のための技術者制度検討会」第13回検討会資料5-2「現状の課題」で報告しています。 電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。
電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。 電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。
電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。 ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。
ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。 普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。
普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。 本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。
本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。 電力会社や工場、ビルなどの電気工作物の保安監督を行える電気主任技術者(電験)有資格者は、第二種、第三種ともに、中長期的にも想定需要に対して十分に存在していると経済産業省は発表しています。
電力会社や工場、ビルなどの電気工作物の保安監督を行える電気主任技術者(電験)有資格者は、第二種、第三種ともに、中長期的にも想定需要に対して十分に存在していると経済産業省は発表しています。